「仕事が苦痛」な日本人の病
毎日すさまじい数のビジネスパーソンが行き交うことから「社畜川」などと揶揄(やゆ)されている、JR品川駅内のコンコース。そこに並べられた「今日の仕事は、楽しみですか。」というデジタルサイネージが、批判を受けて1日で終了になった。
「仕事なんだから楽しいとか、楽しくないとか関係ねえだろ」
「凹んでいるときに見たらメンタルをやられる」
という不快さを訴える声で炎上し、「社畜回廊」などという絶妙なネーミングもつけられて、コピーをイジる大喜利まで始まってしまった。「今日の仕事は、楽しみですか。」という広告が炎上
この結果は当然だ。実は企業の人事担当者の間では、日本人が世界でも有数の「仕事を楽しみにしていない国民」であることは、ずいぶん以前から常識となっている。
例えば、世界77カ国を対象に「考え方」を調べる「世界価値観調査」で、日本人は他のさまざまな先進国を抑えて、「余暇」が重要だと考える労働者が突出して多いことが分かっている。「ワーカーホリック」「企業戦士」などと呼ばれるが、実はそれは仕事が好きだからではなく、義務と責任で「嫌々働かされている」という現実が浮かび上がっている。
また、NHK放送文化研究所が1993年から参加している国際比較調査グループISSPでも、日本人の仕事の満足度はかなり低い結果が出ている。2005年調査での満足度は73%で、世界32カ国と地域中28位。15年の調査では満足度はさらに落ちて60%。「ああ、かったりい」「こんな仕事やりたかねえよ」と愚痴をこぼしながら重い足取りで職場へ向かう人がかなり多いのが、日本の特徴なのだ。「オレは仕事が好きでしょうがない、会社に行くたびにワクワクすっぞ」という意識高い系の方もおられるかもしれないが、日本人の「仕事嫌い」を示す調査は例を出せばキリがない。
さて、そこで気になるのは、なぜ日本人は他国の人よりも仕事を苦痛に感じているのか、ということではないか。
「日本人は生真面目すぎる」「働き方改革が進んでいないからだ」などいろいろご意見があろうが、筆者は「仕事」に対して、他国の労働者にはちょっと理解し難い、カルト宗教のような独自の信仰を持っているからだと思っている。
それは「人は金のためだけに、働いているわけではない」という強烈な思い込みだ。
お金のために働く
「仕事が辛い」のは、どの国の労働者も抱えている悩みだ。が、日本人ほどメンタルをやられないのは、ポジティブシンキングだからではなく、「お金のため」と割り切っていることが大きい。労働の対価として賃金がもらえるので、時間が奪われることや、理不尽なことにもどうにか耐えているのだ。
しかし、独自の信仰を持つ日本人は違う。もちろん、お金はもらいたいが、労働に「働ける喜び」「やり甲斐」「成長が実感できる」、さらには「みんなが喜んでくれる」などという、精神的な幸福をやたらとのっけてしまう。これが他国と異なる最大のポイントなのだ。
それを示すデータもある。パーソル総合研究所が日本を含むアジア太平洋地域14の国・地域で、「仕事を選ぶ上で重視すること」を調査したところ、日本をのぞく13カ国でほぼ似たような傾向になった。
細かな違いはあるが、だいたい「希望する収入が得られること」がダントツに多い。もしくは「仕事とプライベートのバランスが取れること」がトップになる。つまり、あくまで「仕事」というのは、望む賃金を得る手段にすぎず、日常生活と切り分けて考えているのだ。
しかし、日本だけが違っている。1254ポイントで「希望する収入が得られること」が一応トップだが、他国ではまったく上位にこない「職場の人間関係がよいこと」(1230ポイント)がほとんど変わらず、同じく他国の労働者がまったく重視していない「休みが取れる/取りやすいこと」(1136ポイント)と並ぶのだ。
つまり、日本人にとって、仕事とは日常生活のど真ん中なのだ。お金も欲しいが、それと同じくらい重要なのが、人間関係に悩まずに楽しい時間が過ごせるのか、しんどくなったら休めるか。プライベートと切り分けるどころか、仕事が「人生の中心」にあるのだ。
このような「人は金のためだけに、働いているわけではない」というクセの強すぎる労働観が、先進国最低レベルでいよいよ韓国にまで抜かれた「安いニッポン」をつくってきた、と筆者は考えている。
世界の常識が通用しない
世界では「仕事が辛い」という労働者たちの苦しみを和らげるのは、とにかく「賃金」だという考え方が強い。だから、先進国でも順調に最低賃金を引き上げるなどして、賃上げをしてきた。無論、「賃上げしたら中小零細は倒産して、失業者があふれかえるぞ」と騒ぐ経営者もたくさんいたが、政府は引き上げを断行した。
デービッド・アトキンソン氏が『最低賃金引き上げ「よくある誤解」をぶった斬る』(東洋経済オンライン 19年10月9日)の中で紹介しているように、ノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマン教授をはじめ、最低賃金が低い国が、最低賃金を引き上げても雇用に悪影響を及ぼすという証拠は存在しない、または雇用に及ぼす影響が極めて小さいことを示すエビデンスがそろってきたからだ。
冷静に考えれば、これは当然だ。最低賃金の引き上げで経営が苦しくなるような企業が従業員を解雇しても、その人はずっと失業しているわけではない。むしろ、これまでより遥かに条件のいい職を得る機会になるだけだ。だから、世界では当たり前のように賃上げをする。劣悪な労働環境だと叩かれることの多い、アマゾンも日本円で時給2000円程度まで上がっている。
しかし、日本ではこういう世界の常識が通用しない。
なぜこうなるかというと、この国はいまだに科学より宗教が勝っているからだ。世界のエコノミストたちの最新の経済分析より、「賃上げだけが労働者を幸せにするわけではない」というふわっとした話のほうが聞いていてしっくりくる。安心するのだ。
異常な仕事観
多くの日本人にとって仕事とは生活のど真ん中であり、「人生の中心」でもあるので、それがなくなってしまう、減っていくことが何よりも恐ろしい。だから、最低賃金以下しか払えず、ビジネスモデルも破綻した企業であっても、常軌を逸したブラック労働を強いるような企業であっても、とにかく「倒産しない」ことが「善」である。
この「善」を成すために、多少の犠牲があってもしょうがない。だから、経済評論家や中小企業経営者の皆さんは、「生活できない」と訴える低賃金労働者をこう諭す。
「賃金を上げろ、上げろ、とワガママを言うけど、会社が潰れちゃったら元も子もないでしょ。賃金をあげてもいいけど、クビになったり、シフト減らされたら同じでしょ? じゃあ、ガマンしなくちゃ」
そこで不思議なのは、なぜこんな「異常な仕事観」が社会の一般に常識になってしまったのか。経済評論家なんかはすぐに松下幸之助などを引っ張り出して、「日本の高度経済成長を支えた日本の家族主義だ」みたいな方向へ持っていくが、歴史的事実としては、太平洋戦争末期の「皇国労働観」をいまだに引きずっている側面が強い。
実は明治時代まで、日本人の仕事観はもっとシンプルだった。高い技術を持っている人間はたくさんお金をもらえた。自分を高く評価してくれる場所があれば、今の仕事を放り投げ出して、フットワーク軽く移籍した。今で言うところのジョブ型雇用である。
しかし、「富国強兵」という国策のもと、労働者は転職せず、一つの会社で生涯、技術を磨き、後進を指導すべし、というようなトレンドが出てくる。金で優秀な技術者が頻繁に動くようであれば、国全体の技術の底上げはつながらない。また、今問題になっているように、海外への「頭脳流出」という問題も出てくるからだ。
「やり甲斐搾取」と丸かぶり
そこで労働者を会社に縛りつけておくためのシステムとして誕生したのが、「年功賃金」、いわゆる年功序列である。義務教育では教えてくれないが、この労働文化が一気に普及したのは、「戦争」だ。戦後の労働問題を研究し続けた東京大学名誉教授の氏原正治郎氏はかなり早い段階から指摘していた。
『年功賃金が生まれたのはいつか。人によって見方がちがうが、東大の氏原正治郎教授は「第二次大戦中の賃金制度からとするのが通説」という』(読売新聞 1975年2月19日)
新しい年功賃金というシステムが導入されると当然、これまで高い技術などを評価されてそれなりの賃金を得ていた人や、過酷な労働の対価で賃金を受け取っていた人たちから不満の声が上がる。大して仕事もしないのに、社歴が長いだけで高い給料がもらえるシステムなど不条理すぎる。現在の「働かないおじさん」への不満は実は戦時中から存在していたのだ。
そんな「賃金」への不満を一気にゼロにするために生み出されたのが、「皇国労働観」である。
つまり、年功賃金の不平等さを誤魔化すため、「金のために働くのは賤(いや)しい者がやること」という「思想教育」を国民に施すようになるのだ。この徹底した「賃金軽視カルチャー」が、国民総動員の動きもあって、疫病のように日本人の間に広まってしまう。1944年に、厚生研究会によって発行された『国民徴用読本』(新紀元社)にもこうある。
『勤労を賃金を得るための手段と考へれば苦痛が伴ふし、屈辱も感ずることにならう。然し勤労そのものが目的であれば苦痛もなければ屈辱もない。いはゆる「勤労三昧」の境地に到達するものといふべきだ』(45ページ)
これを見て、デジャブを感じないか。そう、まさしくブラック企業が社員を洗脳する際に、よく用いる「やり甲斐搾取」という手法と丸かぶりなのだ。仕事は賃金を得るためではなく、夢や自己実現のためである。そういう思いで働けば、どんな辛いことでもできる――。
そんな思想を研修などで繰り返し叩き込まれ、気がつけば「低賃金で文句を言わずに働く奴隷」にされてしまう。かつて日本では国家がそれをやっていたのである。
カルトから抜け出すこと
「そんな昔のことをアツく語られてもねえ」とシラけている方もいらっしゃるだろうが、ではなぜわれわれはそんな昔につくられた「年功賃金」を今も後生大事にしているのか。戦時体制の都合でつくられた大昔の賃金システムを、「日本企業の強さの秘密」などと崇(あが)めているのか。
年功序列、年功賃金などなくても成長をしている国など世界に山ほど存在しているにもかかわらず、これをやめようと言い出しただけで、「日本を滅ぼす気か」と袋叩きにされ、「年功序列があったから日本は成長できた」という科学的根拠ゼロのストーリーを盲信している。こういう状態を世界では「宗教」と呼ばれる。
70年以上も経過しているにもかかわらず、われわれがいまだに「年功賃金教」を信仰している事実がある以上、同時期に生み出された「皇国労働観」という洗脳からも解けていない、と考えるのが筋ではないのか。
真面目な日本人は、戦時中の指導者たち唱えた「勤労三昧の境地」を今もしっかりと実践している。カネのために働くのではなく、「働く」こと自体を目的化して、「やり甲斐」「働く楽しさ」を重視しているが、なぜかちっとも苦痛が和らがない。むしろ、カネ目当てで働く国の人よりも遥かにメンタルをやられて、「今日の仕事は、楽しみですか。」という問いかけに、不快になったり、心を傷つけられたりする人もたくさんいる。
カルトにハマったまま、いくら「改革」を叫んだところで洗脳は解けない。まずやるべことは、カルトから抜け出すことだ。
賃上げは労働者のワガママ、会社や社会、ひいては国家の利益のことまで考えが及ばない短絡的な発想だ――。そんな宗教裁判のような弾圧を続けてきた結果が、フルタイムで働いても年収200万円程度という低賃金労働者があふれる「安いニッポン」だ。
この現実を真摯(しんし)に受け止めて、そろそろ「人は金のためだけに、働いているわけではない」というブラック企業の研修で連呼させられるよう考え方を日本人は改めるべきではないか。



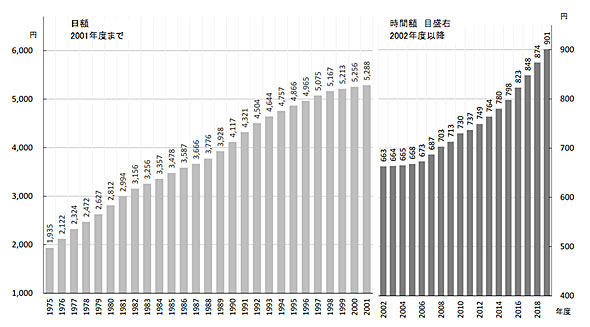


“「仕事が苦痛」な日本人の病” への2件の返信