山で生きる祖父が体現していた、本当の意味での「稼ぐ力」

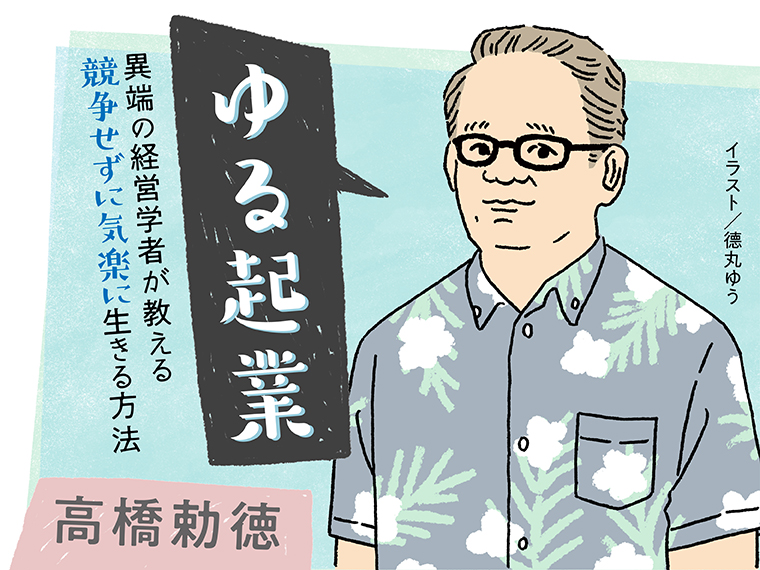
 イラスト/德丸ゆう
イラスト/德丸ゆう
祖父の謎
今ではダムの底に沈んでしまっていますが、四国山脈の山深く、愛媛県と高知県の県境付近に位置する富郷村に、私の父親の実家がありました。私は物心ついた頃から、小学生の間は月に1、2回は父に連れられて祖父の家に遊びに行っていました。
「朝だぞ、起きろ!」
確か小学校1年生の頃です。祖父の家に泊まった夏休みの早朝、前日に山で遊び疲れて熟睡していた私を呼ぶ声が聞こえました。
祖父の声だと思いましたが、同時になんか鼻の周りがくすぐったい。
瞼を開けると、目の前に茶黒い何かが這いずり回ってました。
「うぉっ! 何?」
跳ね起きた私を見て、祖父は笑いながら言いました。
「みーくん、よく見てみろ」
今も昔も、小学生の夏のアイドル、立派なオスのカブトムシでした。
前日、同年代の従兄弟たちと網を片手にカブトムシやクワガタムシを探して、空振りしたのを祖父は覚えていたのでしょう。カブトムシを採って来てくれたのです。
「ほれ、虫かごに入れとけ」
祖父は竹で作られた自作の虫かごを私に渡して、満足げに山に入っていきました。
この時の祖父は、作業服の上下に鉈とザイルを腰からぶら下げていました。おそらく自分の山林で枝打ちか下草刈りをしている中で、カブトムシを見つけて、手づかみのまま私のところに持ってきたのでしょう。私がこのカブトムシを持ち帰って、寿命で命尽きるまでのひと夏、大事に飼ったことは言うまでもありません。
祖父は明治末期の生まれで、第二次世界大戦にも徴兵され、歩兵として中国大陸に渡り、幾つかの勲章も授与された軍人でした。父にとっては、明治生まれの軍人出身者らしく厳しく怖い人だったそうですが、孫である私にとっては、父と並んでアウトドア(山)での生活と遊びを教えてくれる師匠のような人でした。
早春には筍や山菜採りと畑作り、夏はお茶摘みや川での渓流魚採り、秋から冬にかけては畑でサツマイモや柿を収穫して、保存食の干し芋や干し柿作り。祖父にとっては毎年繰り返している生活サイクルの一つでしかありませんが、そばで見て、時々手伝わせてもらうだけですごく楽しい。納屋には農具だけじゃなく狩猟用の罠やマムシの入った酒瓶、自作の水中銃まで無造作に置かれていて、それを弄っていると「コラっ!」と怒られた後、イノシシを捕るための罠の仕掛け方や、アマゴや鮎の突き方を教えてくれたりしました。
小さな頃の私は、祖父が「ロビンソン・クルーソー」的な自給自足の生活をしている人なんだと思っていました。ただ、小学校も高学年になるくらいの頃には、それはありえないとわかるようになります。山の実家には電気もプロパンガスも引かれていましたし、そもそも私を含めた孫たちはお年玉をもらっていました。
父の実家の居間には、祖父が第二次世界大戦時の軍服姿の写真と勲章がいくつかあったので、軍人年金で自給自足しつつ悠々自適の生活をしていたのかというと、それもおかしい。というのも、連載第一回に登場した私の父は、終戦した年に生まれた10人兄弟の三男です。少なくとも、終戦後から10人兄弟の最後の一人が巣立つまでの数十年間、祖父と父の兄弟達は富郷村で稼いでいたはずなのです。
山で「生きていける力」=「稼ぐ力」
「まぁ、いろいろじゃな」
小学校6年生の頃、思い切って「おじいちゃんの仕事って何なのか」を聞いてみたところ、祖父が困ったなぁという感じで、しばらく唸ったあとに出た答えがこれです。
「じいちゃんもワシも、山だったら生きていけるんよ」
すぐそばで話を聴いていた父が、笑いながら答えました。
「まぁ、そうじゃな。みーくんも、どこででも生きていける力を勉強せなあかんぞ」
祖父はそう言いつつ、お手製の番茶を啜っていました。
祖父の言う「どこででも生きていける力」というのは、12歳の少年であった私にとっては大問題に思えるパワーワードです。ましてや、「山だったら生きていける」なんて聞くと、どうすれば良いのか、余計に気になります。
帰り道の車内で父に、「山でいろいろやって、生きていく」ということがどういうことなのかを聞いてみたのですが、これがどうにも要領を得ません。例えば、父が私と同じ年頃の頃、山を切り開いて畑を耕していた話、テレビを買うために兄弟総出で木炭作りをした話、食べられる山菜と食べられない山菜の見分け方の話などなど、色々な話を聞かせてくれたのですが、それが「どこででも生きていける力」にどうつながっていくのかがわからない。
「じいちゃんもワシも、ナイフ一本あったら山で生きていけるからな」
父は最後にそう言いましたが、祖父は元軍人、父親は180cmオーバーのマッチョだったので、小学生の私には、ランボーのようにならないと、山では生きていけないと思えました。
それから40年以上の時が過ぎ、首都大学東京(現東京都立大学)の准教授に着任していた私は東京都檜原村を訪ねていました。当時、地域活性化と社会企業家をテーマにフィールドワークを続けていた中で、東京都の木材で高性能住宅を提供するTOKYO WOOD普及協会に出会い、木材を提供する山主の方にインタビューをお願いしていたのです。
都心部から1時間半ほどの距離にある檜原村ですが、現代的な小洒落た部分もあるものの、かつて私が通っていた祖父の実家とどことなく雰囲気が似ていました。山主さんの自宅も、敷地内にコテージやBBQスペースがあったりするのですが、庭に松やツツジが植えられ、木炭を作るための窯があったりします。建物の現代的な部分を抜いてしまえば、本当に祖父の家とそっくりでした。
「車で走っていると、あちこちでツツジが植えられていますけど、このあたりで流行っているのですか?」
一通りインタビューを終えた後、檜原村を訪れるまでの間、あちこちで目についたツツジについて山主さんに尋ねると、意外な答えが返ってきました。
「昔、ツツジが流行って、売れていたらしいよ。だから、その時期にあちこちでツツジを植えたんだよ」
この山主さんの一言から、祖父が庭先に大量に植え、世話をしていたツツジの生け垣が脳裏に浮かぶとともに、40年越しの疑問が氷解しました。そういえば、祖父の家の庭にも、ツツジが大量に植えられていたのです。
高度経済成長期に住宅需要が爆発した頃、国産の杉やヒノキの木材は飛ぶように売れていました。その頃は、角材一本が平均的な労働者の日当一日分で売れたと言われています。一般的にイメージするような林業家の仕事として、山林を伐採して木材を出荷し、植林していくことで「稼いで」いました。
しかし、多くの木造住宅が外国産材を利用するようになった80年代には、林業自体は「稼げない」仕事になりつつありました。その時、山主さんたちはどのように生活していたのかというと、その時々で山で採れるものを見つけては、現金に変えてきた訳です。
「まぁ、いろいろじゃな」という祖父の言葉は、ほんとうに「そのまま」の意味だったのです。
「この10年は木炭が売れているね。都内には炭火を売りにしている焼鳥屋や焼肉屋が増えてきたから、少し拘りのあるお店だと良質な木炭を欲しがるんだよ」
山主さんはそうも言いました。実は我が国で全国の家庭にガスが供給されるようになったのは、1970年代後半からです。それまで、家庭の主な熱源は木炭と薪でした。父が話してくれたように、その頃は確かに、間伐材を利用して木炭を作り売れば高級品のテレビが買えるくらい「稼げた」のです。
ガスの普及とともに、木炭ビジネスは廃れてしまいました。しかし、時代と状況が変わって、また売れるようになると、檜原村の山主さんたちは木炭を焼き始めています。山主は林業だけで生きている、という現代的な職業への固定観念から、山から得られる色々な資源を稼ぎに変えて、そのミックスで生活していくという、当たり前の行動を見落としてしまっていたのです。
山が「一番快適な状態」を教えてくれる
キャンプ好きの芸人が山を購入したことから、山林を購入する人が増えつつあります。
とはいえ、山林は保有しているだけで固定資産税がかかりますし、伐採や林道の整備などをマメに行わないと、キャンプで利用するのも困難なジャングルになってしまいます。山林は意外に安いので手を出したけど、コストばかりがかかってしょうがないから手放そうとしたら売れずに困っている、という人も出てきているようです。
他方で、実際に自分の山に住んでいる山主さんの多くは、自分の山林を手放すことなく、大事に手入れを続けています。先祖代々受け継いできた山だから、山を維持することで水資源と景観が維持されるのだから、とロマンや理念に基づく美談で語られることも多いですが、ロマンではお腹は膨れません。大事なことは、山と上手く付き合い、生きていくに必要な分くらい稼いでいくことです。
じゃあ、山と上手く付き合うということは、どういうことなのでしょうか? そのヒントをくれるのがPetersら(2009)の、以下の論文です。
Peters, M., Frehse, J., & Buhalis, D. (2009). The importance of lifestyle entrepreneurship: A conceptual study of the tourism industry. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 7(3), 393-405.
企業家がなぜイノベーションから利益を得られるのか。簡単に言ってしまうと、今まで利益を生み出す「価値」とは思われていなかったモノを、「こんな利用価値があるよ」とサービスや製品という形で提示していくからです。この意味で、企業家は私達の日常世界と、生き馬の目を抜くような利潤の奪い合いをしている市場との境界に位置して、「新しく売り込めるもの」を日常世界から市場に持ち込むブローカー的な役割を果たしているといえるでしょう。山主さんたちは、山で育まれる様々なものを、市場に持ち込んでいくことで「稼いで」いく企業家であると言えます。
その上でPetersらは、近代的・合理的な経営手法の拒絶がライフスタイル企業家に共通する特徴であると指摘しています。第一回でもお話したように、起業してある程度稼げるようになると、当然、商売仲間や投資家、銀行から「もっと稼げるから、投資して事業を拡大しないか?」という誘いも多くなってきます。ライフスタイル企業家は、これを「罠」だと考えて拒んでいきます。投資を受けて商売の規模を大きくしていくと、投資家や株主、取引先やお客様に対する責任もどんどん大きくなってしまう。従業員を食わせるために、同業他社と競争して市場シェアを拡大していくことも求められてしまう。そうこうしているうちに、売上高の増大と引き換えに、自分の「稼ぎ」の基盤となっていた趣味や生活スタイルそのものが壊されてしまいます。
もちろん、日常世界と市場との接点を維持しておかなければ、「稼ぐ」ことはできません。そこでPetersらは、ライフスタイル企業家は生活の質と稼ぎがちょうどよくバランスするところが「一番快適な状態」であると判断して、意図的に成長も競争も放棄すると結論づけています。
ところで、生活の質と稼ぎのバランスをとるというと、当たり前のことだと思えますがこれが難しい。私達には程度の差こそあれ金持ちになってみたいという欲があります。市場の持つ魔力はその欲を刺激して、簡単に私達を「稼ぎまくる」方向に駆り立てていきます。その先にあるのが、「仕事の充実と成功が人生の喜び」と考える、一昔前の価値観であると言えます。しかし、ゆる起業の立場から言わせれば、それは市場という魔物に身も心も支配され、自分自身や周りの仲間達までを「資源」として食いつぶしながら、売上の拡大を精神的充実として錯誤していく修羅の道です。
祖父を始めとした山主さんたちが修羅道に落ちないのは、自分が「一番快適な状態」であるかどうかを確かめる、判断基準として山を持っているからです。山が産み出してくれる資源は有限です。儲かるに任せて山で採れるものを売りさばいていくと、すぐに再生不可能な状態の禿山になってしまい、生活が成り立たなくなる。だから山で生きる人たちは「山を守れるか?」を判断基準に持ちます。いわば、「どれくらいの稼ぎが適切なのか」は、山が教えてくれるわけです。山から「何が売れるのか」を知っているだけでは半人前、「これくらいの稼ぎを維持しよう」と山と対話できるようになって初めて、「ナイフ一本あったら山で生きていける」と言える達人になれるわけです。
ゆる起業を目指すにあたって、自分の判断基準になってもらえる外部と「対話する」ことは、すごく大事なことだと思います。この対話するという感覚は、マーケティングや経営戦略が発達し経営手法が高度化し、「仲間」が「メイン顧客」や「顧客」、「競合相手」などの役割が与えられる中で、利益を求める「交渉」に入れ替わってしまいました。ゆる起業を上手くやっていくためには、私の祖父にとっての山のように、大事にしているお客様とか仲間たちなど「稼がせてくれる」全ての他者との対話によって、自分にとって「一番快適な状態」を見出していくことが必要不可欠であると思います。
連載第5回は7/18(月)公開予定です。